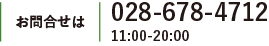【静かに進行する筋肉量の低下】あなたは気づいていますか?
ご覧いただきありがとうございます。
健康管理教室 walk on、健康運動指導士の平野太一です。
walk onコラム第47弾では、見過ごされがちな体の変化、「筋肉量の低下は静かに進む」というテーマでお届けします。
◆ その不調、筋肉が原因かもしれません
「階段がきつくなった」「背中が丸まりやすい」「最近すぐ疲れる」──
そんな変化を感じていませんか?
加齢のせいと思いがちですが、実はこれらは筋肉量の低下によって起きる変化である可能性が高いのです。
◆ データで見る、年齢とともに進む筋肉減少
筋肉は20歳前後をピークに、少しずつ減っていきます。
-
30歳を過ぎると、年間1〜2%の割合で筋肉量が減少
-
下半身の筋肉は特に落ちやすく、65歳以降はそのスピードが加速
-
75〜79歳でのサルコペニア有病率は約22%、80歳以上では**男性32%・女性48%**にも上ります
-
サルコペニアを患うと、死亡リスクが男性で約2倍、女性で約2.3倍、要介護リスクは1.6〜1.7倍に上昇
(出典:J-Stage、日本医科歯科大学、五木田病院ラジオ)
つまり、筋肉の減少=老化の加速であり、日常の快適さや将来の生活の質にも直結する重大な問題なのです。
◆ 筋肉が減るとどうなるのか?
筋肉量の低下は、見た目だけでなく体の機能そのものに影響を及ぼします。
-
疲れやすくなり、活動量が減る
-
転びやすくなり、転倒→骨折→寝たきりのリスクが上昇
-
姿勢が崩れやすくなり、腰痛・肩こりの原因にも
-
筋肉の減少は代謝を低下させ、生活習慣病の悪化にもつながる
こうした悪循環を断ち切るためには、「筋肉を維持・強化すること」が不可欠です。
◆ 運動で筋肉は何歳からでも増やせる!
ここで朗報です。
筋肉は、年齢に関係なく鍛えることで増やすことができます。
-
60〜72歳の方を対象に行われた12週間のトレーニングでは、膝を伸ばす筋力が227%もアップ
-
厚生労働省の報告によれば、週2〜3回の筋力トレーニングで筋力・骨密度・身体機能の改善が見られるとのこと
(出典:Venus Comrade、厚生労働省レビュー)
つまり、「もう遅い」は誤解です。今からでも、遅くはありません。
◆ 今行動することで、未来が変わる
60代は体の変化を最も感じやすい時期です。
「まだ大丈夫」と思って何もしないままでいると、筋肉の減少は加速します。
一方で、今からでも適切な運動を始めれば…
-
70代・80代になっても旅行や趣味を楽しめる
-
孫と一緒に外で元気に遊べる
-
自分の足で歩き続けられる
そんな未来が現実になります。
◆ 【まとめ】筋肉は「人生の資産」
筋肉は、貯金と同じように「今から少しずつ積み重ねていくこと」ができます。
今日から始める一歩が、将来の安心と自立した生活を支える大きな力になります。
「いつまでも自分の足で歩きたい」
その願いを叶えるために、一緒に筋肉の“資産づくり”を始めましょう。