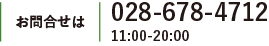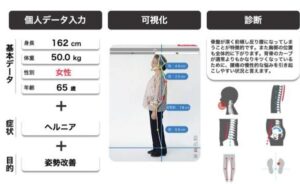【2025年の夏は危険レベル】熱中症を防ぐために今すぐできる対策
こんにちは。宇都宮でフレイル・生活習慣病・認知症の予防に力を入れている運動施設・健康管理教室「walk on」代表、健康運動指導士の平野太一です。
毎年お伝えしている「熱中症対策」ですが、今年は例年以上に注意が必要です。
というのも、2025年の夏は**「過去にない危険な暑さ」**が予想されており、これまでの感覚で過ごすと体に深刻な影響が出かねません。
実際、30代の運動経験者でも倒れるほどの暑さが続いており、もはや「若いから大丈夫」とは言えない時代です。
そこで今回は、「正しい水分と塩分の補給方法」だけでなく、「見逃しやすい初期症状」についても改めて解説します。
◆ 熱中症とは?屋内でも起こり得る命に関わる症状
熱中症とは、体温調節がうまくいかなくなり、体温が異常に上昇してしまう状態です。
特に高温多湿かつ風の通らない環境では、室内であっても油断はできません。
◆ 熱中症の4段階とその症状をチェック
🔹1.熱疲労(初期段階)
-
発汗が多くなる
-
頭痛・めまい・吐き気
-
身体のだるさや足の重さ、ふらつき
👉 この段階での早期対応がカギ。涼しい場所で休み、水分・塩分を補給すれば回復が見込めます。
🔹 2.熱痙攣(筋肉のけいれん)
-
発汗によって塩分が失われ、筋肉がけいれん
-
数秒~数分続くこともある
-
経口補水液を飲み、静かに安静を保つことが大切です
🔹 3.熱失神(意識の異常)
-
急激な血圧低下により、立ちくらみや一時的な意識消失が発生
-
「一瞬意識が遠のいた」場合、すでに危険な状態です
-
涼しい場所で横になり、速やかに水分と塩分を補給しましょう
🔹 熱射病(命にかかわる重症)
-
体温が40℃以上に上昇
-
意識が混濁し、皮膚が乾燥・呼吸異常・心拍の乱れが現れる
-
迷わず救急車を呼ぶべき状況です
◆ 熱中症を防ぐための5つの習慣
✅ 1. 正しい水分と塩分の補給を意識する
-
単なる水だけでなく、塩分と糖分を含むスポーツドリンクや経口補水液を選びましょう
-
お茶やコーヒーには利尿作用があるため、別に水や補水液を補うことが必要です
-
また、外出時にはゼリータイプの補水食品も便利です
-
さらに、一気飲みではなく、こまめに少量ずつ飲むことが基本です
✅ 2. 暑さを避けるための行動をとる
-
日中の外出や運動はできるだけ避けましょう
-
室内では冷房を我慢せず使用し、設定温度は28℃以下を目安に
-
日傘・帽子・冷感タオルなどを活用して直射日光を避けることも効果的
-
加えて、通気性の良い服装で体の熱を逃がす工夫も大切です
✅ 3. 「暑さに強い体づくり」は無理にしない
-
体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」も必要ですが、無理は禁物です
-
初夏のうちから、涼しい時間帯に軽く体を動かす習慣をつけましょう
✅ 4. 食事でミネラルと水分を補う
-
水分とともに塩分・カリウム・マグネシウムなどのミネラルも重要です
-
例えば、味噌汁・梅干し・バナナ・きゅうりなどをうまく活用しましょう
✅ 5. 高齢者や子どもは特に注意を
-
体温調節が苦手な高齢者・乳幼児は特に注意が必要です
-
周囲の大人が、こまめな声かけと体調チェックを行いましょう
◆ 【2025年の夏】最大のリスクは「大丈夫だろう」という油断
今年の夏は、これまでとは比較にならないほどの暑さです。
「自分は大丈夫」と思い込むことが、最も大きなリスクになります。
熱中症は、年齢や体力に関係なく、誰にでも起こり得る命のリスクです。
ただし、正しい知識と予防行動があれば、確実に防げる病気でもあります。
◆ 【まとめ】自分と周囲を守る行動を、今日から
熱中症を防ぐためには、「気づく力」と「備える意識」が何よりも大切です。
そして、自分だけでなく、家族や友人、地域の方々とも声を掛け合うことで、命を守る行動が広がります。
どうか今年の夏は、“これまで通り”ではなく、“新しい感覚”で過ごしてください。
無理せず、賢く、そして安全に。皆さまで猛暑を乗り越えましょう。